【普通に一緒に暮らしている家族が、急に認知症だと診断されたらどうしますか?】
患者さんが認知症である場合、必要に応じて本人や家族にそれを伝えることになる。その際に生じる看護師目線アルアル。
家族に信じてもらえない
認知症の家族がいても本人に自覚がなく、なかなか病院に連れて行けない、なんてことはよくある話だ。むしろ「認知症だから病院に行こう」なんて声をかけたら本人が怒りブチ切れて手もつけられないからどうしたらいいかわからない、なんてご家族もいることと思う。
しかし目線を変えてみると、病院ではまたちょっと違った種類の困った事象が起こる。
家族に認知症だと伝えても信じてもらえないのだ。
認知症になった患者さんはそうでない方よりもADL(日常生活動作:日常生活を送る上で必要な基本的行動)の自立度が下がることがある。また状況を理解する力が衰えて、今どこにるか、何をしているのか、周りにいる人が誰なのかわからなくなったりする。
ちょっとネガティブな例を挙げてみる。
- 会話が成り立ちづらくなる。言葉のキャッチボールがうまくいかず、質問の内容と全く関連性のない言葉が出てきたり、独り言を言い続けたりする。
- オムツの取り替え、体拭きやシャワーなど清潔ケアの際、体に触れられる理由が分からないので、暴力行為や暴言につながる。
- 食欲はあるが自分で食べられなくなってしまった方には、食事の介助を行うが、口に入れたものダーっと出したり、薬を飲むことを拒否したりする。
- 体が丈夫な方は、家に帰ろうとむっくりと起き上がって病院を出て行こうとする(万が一脱院を見逃してしまうと、迷子になる)。
- 「囚われている」「誘拐されている」と自分の携帯で、家族や場合によっては警察に電話してしまう。
家族が認知症であるということを信じてくれないことに、看護師なりたての頃の私はびっくりした。上に挙げたような言動をしている患者さんの家族にも信じてもらえないことは多々あった。医師からの診断は信じてくれないのに、「医療従事者から毎日暴力を振るわれている」という患者さんの言葉の方を信じてしまうのだ。
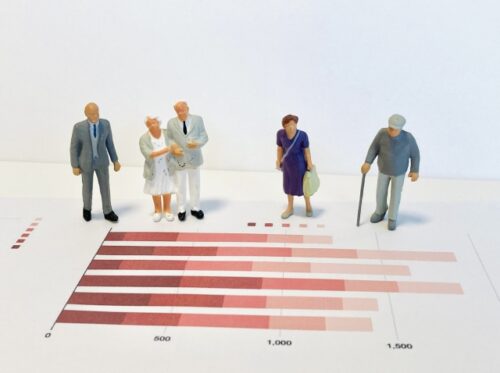
家族が現実を受け入れられない理由
入院中の患者さんについて家族に症状を説明する際に、認知症であることも同時にお伝えする。すると「この病院でひどいことをされて認知症になったんじゃないですか!?」という反論や、そもそも「いえ、うちは認知症ではありません」とキッパリと診断を「断る」方もいる。
家族が認知症になってしまったらショックだし、なかなかその事実を受け入れ難いというのは理解できる。
しかし実は我々看護師も、家族が認知症であることをすんなり受け入れられないことについて一定の理解もしている。それは何故か、、、
家族がお見舞いに来ると、そんな認知症の患者さん達が一時的にスキッとクリアになることがよくある。本当によくある。家族に庭の植物の手入れの方法を教えたり、近所の方の健康を気遣ったりする。会話が成り立っている。こんなに変わるなら、家族が信じられないのも無理はない。
医師側のスタンス
でも家族がお見舞いに来て話してみたら、全くの普通だったということイコール「認知症が治った」とか「認知症ではなかった」ということにはならない。
医師はそれなりの理由があり、自信を持って「認知症です」と伝えているように私には見える。「糖尿病です」「インフルエンザです」「脳梗塞です」「腎盂腎炎です」となんとなくテキトーに伝えることはないのと同じ、認知症であることもなんの根拠もなく伝えてるってわけではなさそう。
まとめ
「うちの家族は認知症なんかじゃないのに『認知症です』とか言いやがって!ふざけんなあのヤブ医者め!」と言いたくなる心境の方もいることとは思う。
早めに認知症であることに気づけた場合、看護師として私が思いつくメリットは以下の通り。
- 不思議に思っていた言動やすぐキレる理由などについて納得感が得られる。
- 早めの対処により、進行を遅らせたり場合によっては改善したりする可能性がある。
- 今後の生活の不安や不自由になる部分について、事前に地域の担当者に相談できる。
- 認知症が進行した場合の生活を想定して、困る前に早めの準備ができる。
もし認知症だと言われたら、「そうか、一見分からないけど認知症なのだな」と、一旦その事実を飲み込んでみることでメリットもありそうだ。
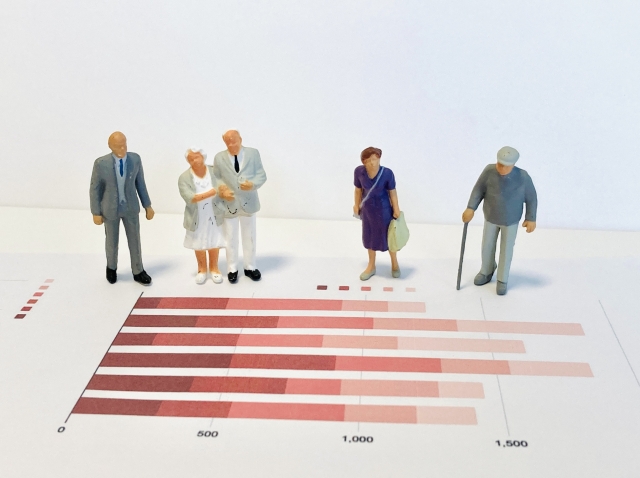


コメント